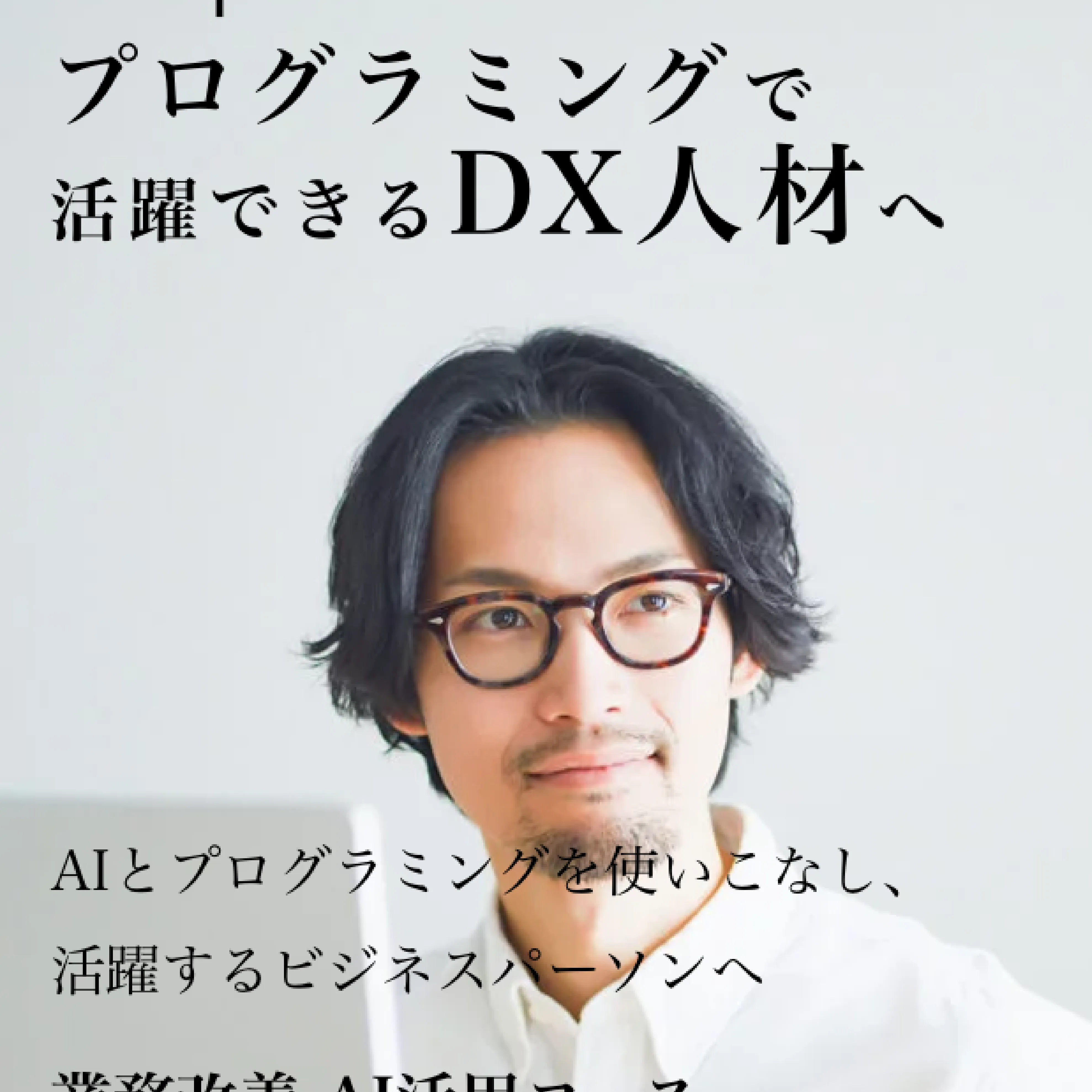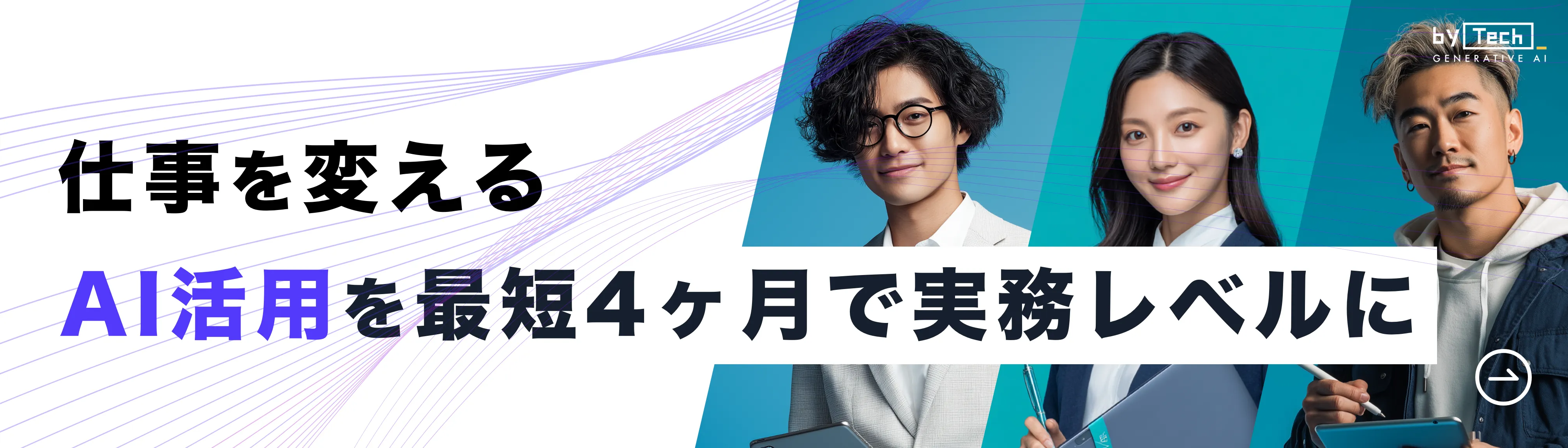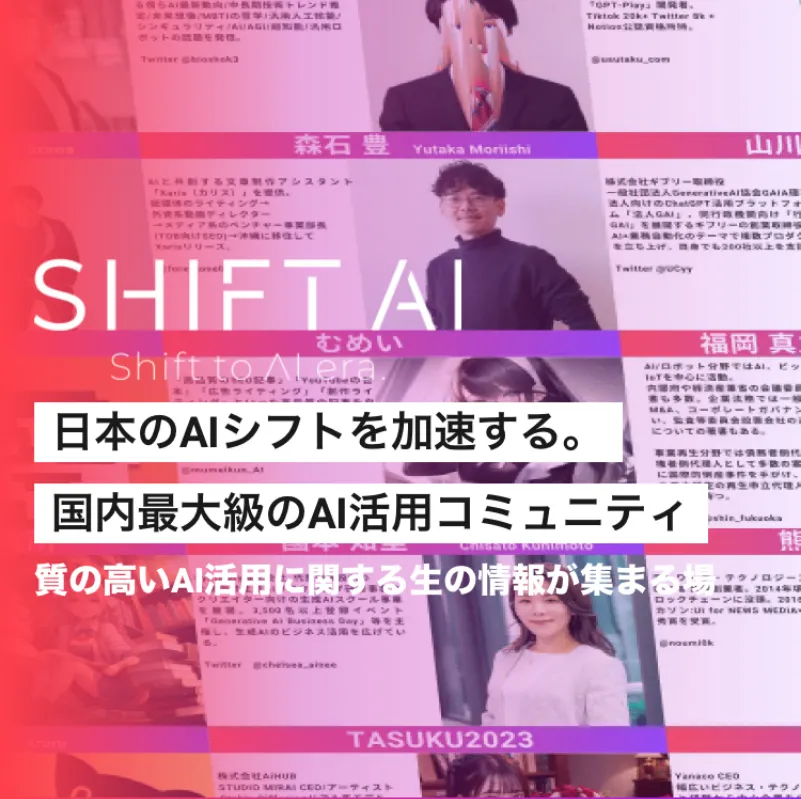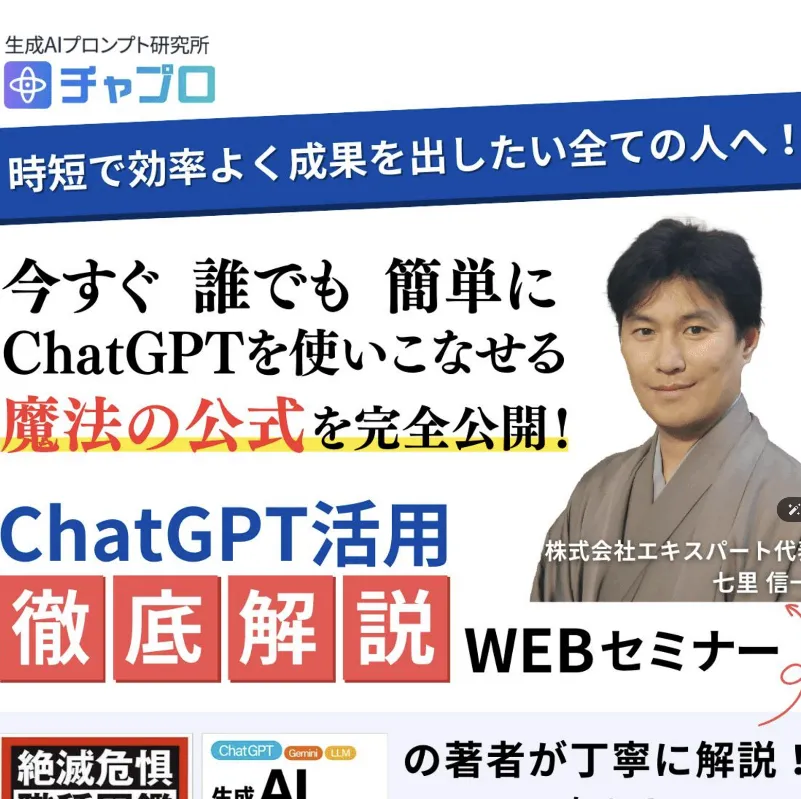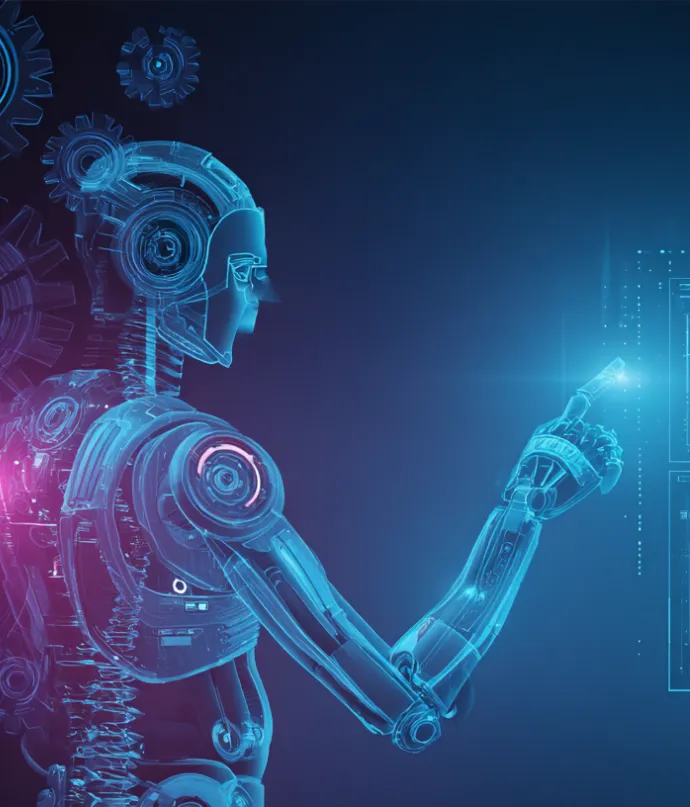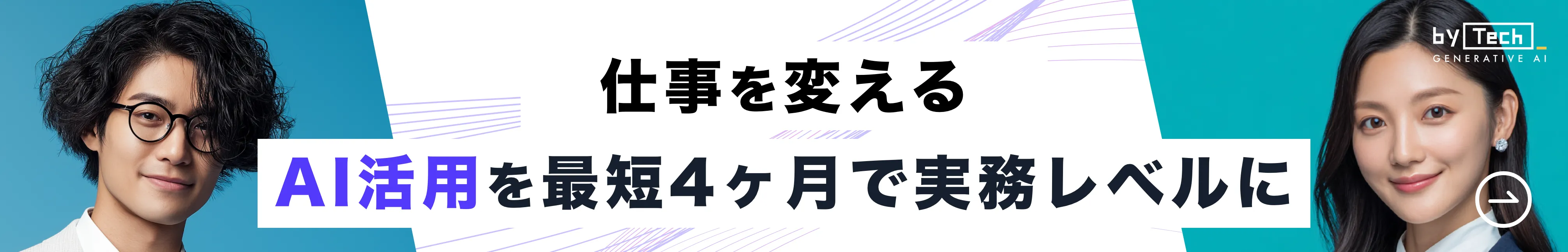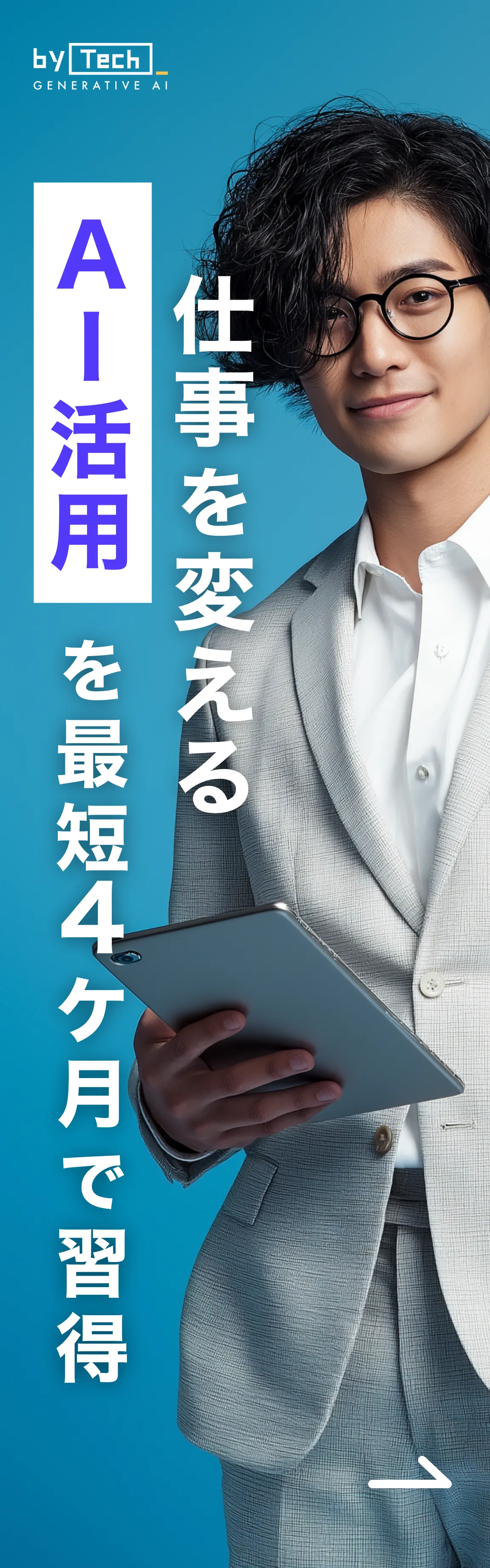Dify(ディフィ)で何ができる? | 社内業務が劇的に変わる活用事例7つを紹介

Dify(ディフィ)とは?初心者にわかりやすく基本を解説
Dify(ディフィ)は、RAG(検索拡張生成)・ワークフロー・エージェントをノーコード/ローコードで組み合わせ、社内向けのAIアプリをすばやく構築できるプラットフォームです。複数のLLMを用途別に使い分けながら、Slackや既存APIとも連携可能。PoCから小規模本番までを短期間で実現しやすいのが特長です。
向いている組織・担当(情シス/業務改善/PM)
情シス・業務改善チーム・PMなど、限られた工数で早く成果を出したい部門に最適です。ベンダーロックインを避けつつ社内データを安全に活用したい企業や、AI活用を部門横断で標準化したい現場に向いています。
効果の要点(スピード/拡張性/運用性)
- スピード:GUIでRAG・分岐・API連携を設計でき、30日以内の小規模本番も現実的。
- 拡張性:エージェント×ツール実行×マルチLLMでユースケースを横展開。
- 運用性:ログ・評価・権限が揃い、継続改善サイクルを回しやすい。
Dify(ディフィ)で何ができる(RAG・ワークフロー・エージェント)
RAGで社内ナレッジ活用
Notion・Google Drive・社内DBなどに散在するナレッジを同期し、根拠(引用)付き回答を生成。検索→抽出→生成を一貫させることで、幻覚を抑えつつ正確性を向上します。
- 主なメリット:最新情報の反映、回答の再現性、監査対応のしやすさ。
- 使いどころ:社内FAQ、製品仕様の照会、手順書の検索、オンボーディング支援。
ワークフローで業務自動化
ドラッグ&ドロップで入出力や分岐、外部API呼び出しを可視化。検証・デバッグがGUIで行え、ガードレール(バリデーション・承認)も挟めます。
- 主なメリット:業務手順の標準化、属人化の解消、変更に強い運用。
- 使いどころ:レポート定期生成、問い合わせ振り分け、チケット起票、データ整形。
エージェントと外部連携
ツール実行・関数呼び出しにより、検索・集計・登録・通知まで自律的に実行。Slackや社内SaaS、CRM/ITSMとの連携で“回答して終わり”から“実行まで”を実現します。
- 主なメリット:担当者の手戻り削減、応答から実務完了までの一気通貫。
- 使いどころ:FAQ回答後のチケット作成、在庫照会→受注登録、承認依頼の自動送付。
複数LLMの使い分け
タスク別に高精度モデル/軽量高速モデルを切替え、品質×コストを最適化。フェイルオーバーやルーティング、キャッシュで安定稼働を支援します。
- 主なメリット:推論単価の抑制、SLA維持、ユースケース拡張の柔軟性。
- 使いどころ:要約は高速モデル、重要文書の起案は高精度モデル、といった役割分担。
Dify(ディフィ)の活用事例7つと得られる効果
CS一次応答/社内FAQ
CS一次応答ボットでは、よくある問い合わせに即時回答しオペレーターは難案件へ集中。社内FAQアシスタントは就業規則や手順書、ツール操作を横断検索して自己解決を促進します。
- 効果:一次応答の自動化率向上、平均応答時間短縮、自己解決率向上、問い合わせ件数の削減。
議事録要約/レポート生成
会議録から決定事項・担当・期限を自動抽出する議事録要約、売上・在庫・広告などのレポート自動生成で定例業務を定型化。更新ミスを防ぎ、可視化を平準化します。
- 効果:会議後の整理時間削減、タスク漏れ抑制、定例レポート作成の省力化。
営業資料ドラフト/Slack連携/申請自動化
過去提案や事例を参照した営業資料ドラフト、/コマンドで検索・要約・翻訳・タスク登録を行うSlack連携アシスタント、稟議のドラフト作成やステータス更新を担う申請・承認フロー自動化で、現場の即応性と統制を両立します。
- 効果:提案速度向上、ナレッジ再利用の促進、リードタイム短縮、入力漏れ・差戻し削減、コンプライアンス順守の強化。
Dify(ディフィ)の始め方5ステップと注意点(費用・セキュリティ)
環境準備→データ投入→設計→モデル選定→評価
- ステップ1:環境準備 — アカウント/権限設計、責任者の明確化、利用形態(SaaS/自社環境)の選定。
- ステップ2:データ投入 — ナレッジ整備、ファイル形式/メタ情報の統一、PIIのマスキング、同期間隔の定義。
- ステップ3:設計 — ユースケース定義、ワークフローの入出力/分岐、ガードレール(制約・承認)の設置、評価指標の設定。
- ステップ4:モデル選定 — 精度/コスト/レイテンシの要件に基づきマルチLLMを選択し、ルーティング/キャッシュを設計。
- ステップ5:評価 — 人手評価+A/Bで改善、ゴールデンセット運用、SLA/品質基準の定期レビュー。
初期費用・ランニングの目安と最適化
主要コストは推論(トークン)・ベクターストア・監視/ログ。初期は小規模で始め、利用量に応じてスケールするのが堅実です。
- 最適化の例:プロンプト/コンテキストの短縮、キャッシュ再利用、バッチ処理、ツール呼び出しのゲーティング、低優先ジョブのオフピーク実行。
- 見積りのコツ:1件あたり平均トークン×月間件数で概算→ユースケースごとに上限値を設定。
セキュリティ/権限/ログの基本
- データ分類と最小権限:秘匿情報はアクセス分離、ロール/スコープで制御。
- 暗号化と秘匿情報管理:転送/保存時の暗号化、APIキーの安全保管、監査証跡の保持。
- ログ/可観測性:プロンプト/応答/ツール実行を追跡し、失敗パターンの早期検知と改善に活用。
つまずきやすい点と回避策
- KPI不在:「自動化率・回答品質・リードタイム」などの数値目標を先に合意。
- ナレッジ品質不足:重複/古い手順の整理、メタデータ付与、更新フローを定義。
- 作り切りで運用停止:定例のレビュー会/改善スプリントを仕組み化。
- 過度な自動化:高リスク処理は人手承認を挟む。フェイルセーフの用意。
まとめ:Dify(ディフィ)を活用して最短で成果つなげる
Dify(ディフィ)は、RAG・ワークフロー・エージェント・複数LLMを一体で扱える実践的な基盤です。情シスや業務改善、PMが中心となり、小さく作って早く回すことで、CS一次応答や社内FAQ、議事録要約、レポート自動化などの効果を短期間で可視化できます。
- まずは高インパクトな1ユースケースを選定(問い合わせ削減やリードタイム短縮が測れる領域)。
- ナレッジを整備してRAG接続(更新フローとメタデータ設計)。
- ワークフローにガードレール(承認・検証・ログ)を組み込み、評価指標を明確化。
- 用途別にLLMを使い分け、精度・速度・コストを最適化。
- ログに基づく継続改善で、品質と効率を段階的に引き上げる。
次の一歩はシンプルです。「FAQ」「Slackアシスタント」「定例レポート」のいずれかを題材に、30日プラン(環境準備→データ→設計→モデル選定→評価)で試すだけ。小さな成功を横展開し、組織全体でAI前提のオペレーションへ移行していきましょう。